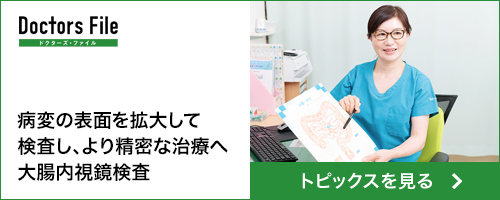生活習慣病とは
日頃の生活習慣の積み重ねによって引き起こされてしまう病気を総称して生活習慣病と言います。具体的には、偏食、嗜好品の過剰摂取(喫煙、アルコールの過剰摂取 等)、運動不足、ストレス、睡眠不足などが蓄積していくことがきっかけとなります。これらが続くことで、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を発症するようになります。
上記の疾患については、自覚症状が現れにくく、病状を進行させやすいという特徴があります。放置が続けば動脈硬化を促進させることになります。それでも何の治療をしなければ、血管狭窄による血流悪化、血管閉塞が起こるようになります。これによって、脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、閉塞性動脈硬化症など重篤な合併症(ある病気の発症がきっかけとなって起きる別の病気)を発症するようになります。
健診結果で数値に異常があれば、速やかな受診を
このような状態にならないためには、定期的に健康診断を受診することが大切です。その結果、生活習慣病に関係する数値(血圧、血糖値、コレステロール値 等)に異常があると医師から指摘を受けた場合は、体に何の異常がないと感じていても一度医療機関を受診されるようにしてください。
当クリニックでも生活習慣病を発症している患者さん、あるいは生活習慣病の予備群であるという方を対象に治療や予防対策を行っています。内容としては、食事療法や運動療法などによる生活習慣の改善、治療が必要な場合は薬物療法を行っていきます。
主な生活習慣病
糖尿病
糖尿病とは
慢性的に血糖値(血液中に含まれるブドウ糖の濃度)が基準の数値を上回っている状態を糖尿病と言います。
そもそもブドウ糖とは、脳や体のエネルギー源となるもので、細胞に取り込まれるとエネルギーとして使われれるようになります。その際には膵臓から分泌されるホルモンの一種であるインスリンの働きが不可欠とされています。そのインスリンが何らかの原因で機能不足を起こし、細胞に取り込まれないまま血液中でダブつくと血糖値は上昇したままになります。これが発症のメカニズムです。
糖尿病は大きく2つに分かれます。ひとつは1型糖尿病です。これはインスリンを分泌するβ細胞が破壊されることでほぼ分泌されていない状態になります。原因としては、自己免疫の異常などが挙げられます。ふたつ目は2型糖尿病です。これは不摂生なライフスタイル(肥満、運動不足、喫煙、過剰な飲酒、ストレス 等)がきっかけとなって発症するタイプです。この場合、膵臓は疲弊しているのですが、それによってインスリンの分泌量が不足する、あるいは量が十分でも効きが悪くなるといった状態になります。ちなみに日本人の全糖尿病患者さんの大半が2型になります。
主な症状ですが、発症初期から痛み等の症状はありません。ある程度、病状が進行すると、頻尿・多尿、異常な喉の渇き、全身の倦怠感、体重減少などがみられるようになります。それでも放置が続けば、細小血管障害による合併症(糖尿病三大合併症:糖尿病網膜症・糖尿病神経障害・糖尿病腎症)、動脈硬化促進による脳血管障害(脳梗塞 等)、心筋梗塞などの重篤な病気を発症することもあります。
治療について
糖尿病治療の目的は、血糖値を基準の数値まで下げ、それをコントロールすることにあります。
1型糖尿病の患者さんでは、インスリンがほとんど分泌されていないので、体外から補充するインスリン注射となります。
2型糖尿病の患者さんでは、まず生活習慣を見直します。食事療法では、適切なカロリー摂取量を守るなどします。運動療法では、1回30分程度の有酸素運動(軽度なジョギング 等)などを行っていきます。上記だけでは、血糖値の改善が困難な場合に併せて経口血糖降下薬による薬物療法となります。それでもコントロールが難しいとなればインスリン注射となります。
高血圧
高血圧とは
血圧とは、心臓から血管(動脈)を通じて、各器官へと血液が送られる際に血管壁に加わる圧力のことを言います。この血圧が基準とされる数値よりも高いと判定されると高血圧と診断されます。その数値に関しては、外来時測定であれば、収縮期血圧(最高血圧)が140mmHg以上、拡張期血圧(最低血圧)が90 mmHg以上としています。判定に関しては一度の測定で決まることはなく、同条件下で複数回測定した後に確定します。
発症の原因については、主に2つあるとしています。ひとつは全高血圧患者さんの9割を占めるとされる本態性高血圧です。これは原因がはっきり特定できない高血圧になります。ちなみに現時点では、遺伝的要因(高血圧になりやすい体質)と不摂生なライフスタイル(肥満、塩分の過剰摂取、喫煙、多量の飲酒、運動不足、ストレス 等)が組み合わさるなどして起きると考えられています。2つ目は、二次性高血圧です。これは、他の病気の発症が引き金となって起きる高血圧です。具体的には、腎実質性高血圧、原発性アルドステロン症、クッシング症候群などの患者さんで高血圧を発症しやすくなります。
よくみられる症状ですが、発症初期から自覚症状はありません。また高血圧の状態というのは、心臓から血液を送る際に余計な負荷をかけなくてはならなくなります。この圧に耐えるべく血管は肥厚化し、内部は脆弱化するようになります。これによって動脈硬化は進行し、さらに放置が続けば、脳血管障害(脳梗塞、脳出血)、心筋梗塞、心不全、腎臓病などの重い病気を合併症として発症するようになります。人によっては、合併症の症状がみられて、初めて発症に気づいたという方も少なくないです。
治療について
治療の目的は、血圧の数値を基準の値まで下げ、それを維持していくことになります。そのためには、まず生活習慣の改善からになります。
食事面では、減塩(1日の塩分摂取量を6g未満)、野菜や魚を中心とした栄養のとれた食事メニューにする、禁煙や節酒に努めるなどしていきます。また肥満の方は心臓に負担がかかるので減量する必要があるので食べ過ぎに気をつけます。
また血圧を下げる対策として運動は有効です。その内容については、ハードな運動量はかえって上昇させてしまうことがあります。そのため、ややきつめの運動に留めます。具体的には、息が弾む程度の有酸素運動(1回30分ほど)で、軽度なジョギングなどです。これをできるだけ継続的に行います。
上記の生活習慣だけでは血圧の数値が改善しない場合は、降圧薬による薬物療法も併せて行います。この場合、患者さんの血圧の状態によって、1種類で済むこともあれば、降圧薬を複数以上組み合わせる必要があることもあります。
高脂血症(脂質異常症)
高脂血症とは
血液中に含まれる脂質(血中脂質)のうち、LDL(悪玉)コレステロールと中性脂肪(トリグリセライド)が過剰な状態にあると判定されると以前は高脂血症と診断されました。その後、HDL(善玉)コレステロール(LDLコレステロールを回収する働きをする)が必要以上に少ないという場合も高脂血症と同様に動脈硬化を促進させやすいことが判明したことで、現在は脂質異常症という疾患名で呼ばれるようになりました。
脂質異常症発症の有無については、空腹時採血による検査で判明します。診断基準については次の通りです。以下のように3つのタイプに分けられます。
- 高LDLコレステロール血症:LDLコレステロールの数値が140mg/dL以上
- 低HDLコレステロール血症:HDLコレステロールの数値が40mg/dL未満
- 高トリグリセライド血症:トリグリセライド(中性脂肪)の数値が150mg/dL以上
体に必要でも過剰であれば動脈硬化を促進
LDLコレステロール(ホルモンや胆汁酸等の原料)も中性脂肪(糖質不足を補う、皮下脂肪になって体温を維持する 等)も体にとっては必要不可欠なものです。ただこれらが過剰な状態になる、あるいはHDLコレステロールが基準よりも減少しているとなれば、血管内にLDLコレステロールは蓄積するようになります。これが動脈硬化を促進させます。
また他の生活習慣病と同様に自覚症状は出にくいです。そのため、健康診断の結果から気づく患者さんが多いです。それでも無症状だからと放置を続けていけば、動脈硬化の進行による血管狭窄や血管閉塞によって、脳血管障害(脳梗塞、脳出血 等)、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞 等)などの重度な合併症を引き起こすこともあります。
発症の原因については、原発性脂質異常症と二次性脂質異常症に分けられます。前者は、遺伝的要因で発症するタイプです。主に家族性高コレステロール血症の発症等によって引き起こされます。後者は、何らかの病気や薬剤等によって発症します。病気に関しては、甲状腺機能低下症(橋本病 等)、糖尿病、肥満などが挙げられ、薬剤に関してはステロイドの長期投与等によるものです。
治療について
治療に関しては、3つの中のどのタイプ(高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高トリグリセライド血症)であっても、LDLコレステロールの数値を下げることが目的となります。同数値を下げることは、他の数値の改善にもつながるからです。
まず生活習慣の見直しから始めます。最も重要なのが食事面(食事療法)です。具体的には、コレステロールを多く含む食品(卵、レバー、魚卵、乳製品 等)は避け、食物繊維を多く含む食品(野菜、海藻、きのこ)は積極的にとるようにします。また高トリグリセライド血症の患者さんは、お菓子やジュース等の糖分を多く含む食品は控え、お酒を飲む方は節酒をします。
さらに日頃から運動をすることは、トリグリセライド(中性脂肪)を下げ、LDLコレステロールを増やす効果が期待できます。運動量については軽度で充分とされ、息がやや上がる程度の有酸素運動(軽度なジョギング 等)を1回30分程度行います。できるだけ毎日行うのが望ましいです。
上記の生活習慣の改善だけでは、LDLコレステロール値が下がらないとなれば、併行して薬物療法(LDLコレステロールを下げる効果のある薬:スタチン系 等)も行います。
痛風(高尿酸血症)
痛風とは
痛風は主に血液中に含まれる尿酸が過剰に増えることで、一部の関節に腫れや激痛の症状がみられる疾患です。なお血液中に含まれる尿酸の状態は採血によって確認できますが、血清尿酸値(血液中に含まれる尿酸の濃度)が7.0mg/dL以上と判定されると高尿酸血症と診断されます。
この尿酸は水に溶けにくい性質で、高尿酸血症の状態になると、針状の結晶を持つ尿酸塩に変化していきます。これが体内のあちこちで増え、関節に溜まるようになると、それを異物と認識した白血球が尿酸塩を排除しようと攻撃します。これによって関節に炎症が起きて腫れ上がり、その部位には激しい痛みが伴うようになります。これを痛風発作(痛風)と言います。なお高尿酸血症の患者さんのすべてが発症するとは限りませんが、そのリスクは非常に高いです。
また痛風発作に関しては、全ての関節で起きる可能性はありますが、足の親指の付け根で起きるケースが大半です。他の部位では、膝や足首などで現れることもあります。痛みについては、発症から24時間をピークに症状は和らいでいき、1週間程度で治まるようになります。ちなみに30~50代の男性に発症しやすく、同発作は再発しやすいという特徴もあります。
発症の原因については、遺伝的要因もありますが、尿酸の元となるプリン体を多く含む食品の過剰摂取、尿酸値を上昇させてしまうアルコールの飲み過ぎや肥満体質といったことが挙げられます。これらによって、体内から尿酸を上手く排出できない、あるいは体内で尿酸の産生が過剰になるという状態になってしまい、尿酸が増えるようになるのです。
治療について
痛風発作による痛みや腫れを治めたい場合は、対症療法による薬物療法としてNSAIDs(非ステロイド抗炎症薬)を使用することがあります。
痛みや腫れが治まったら、根本の原因でもある尿酸値を下げることを目的とした治療を行います。この場合、患者さんの高尿酸血症の状態によって、尿酸排泄促進薬、もしくは尿酸生成抑制薬が用いられます。そのほか、尿酸値を上げないための生活習慣の改善もしていきます。具体的には、飲酒やプリン体を多く含む食品を控える、肥満の方は減量するといったことです。