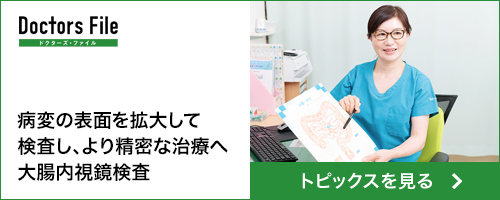消化器内科とは

当診療科は、消化管と呼ばれる、口から肛門まで一本の長い管で構成されている各器官(食道、胃、小腸、大腸 等)で起きたとされる異常や病気について、診察・検査・治療を行っていきます。なお、消化管の消化等の働きを助ける臓器、膵臓、胆のう・胆道、肝臓などにつきましても診療範囲となります。
消化器症状でよくみられるのは、腹痛、嘔吐・吐き気、下痢、便秘などです。これらのケースは、一過性のことも多いので内科で対応することもあります。ただ、上記の症状は重度な消化器疾患でも現れる一症状でもあります。そのため詳細な検査が必要と判断すれば、日本消化器内視鏡学会認定の内視鏡専門医の医師による胃カメラ(上部消化管内視鏡)や大腸カメラ(大腸内視鏡)による詳細な検査をはじめ、腹部超音波検査(腹部エコー)、血液検査等を行うなどして、総合的に判断し、診断をつけていきます。
以下の症状に心当たりがあれば一度ご受診ください
- 胃痛・腹痛
-
- 胃が重苦しい
- お腹が苦しい、おなかが張る
- 差し込む痛み
- みぞおちの痛み
- 胃の調子が悪い
-
- 胃もたれする
- 胃の不快感
- 胸やけがする
- 吐き気がする
- 嘔吐する
- 気持ち悪い
- げっぷがでる
- 食後背中が痛くなる
- 食道のつかえ感
-
- 飲み込みにくい
- 喉がつかえる
- 嚥下障害
- むせる
- 便通異常
-
- 便秘気味
- 下痢を繰り返す
- 便が細い
- 便秘下痢を繰り返す
- 残便感がある
- 血便・黒色便
-
- 排便時に出血
- 血便が出た
- 便が黒い
- 吐物に血が混じる
- 検診で異常
-
- 便潜血
- ピロリ菌
- 肝障害
- 胃レントゲン検査
- 腫瘍マーカーが高値
- 食欲不振
-
- 体重の減少
- 食欲がない
- 疲れやすい
- ふらふらする
- 黄疸(目に見えて白目や肌等が黄色っぽい状態)
-
- 目が黄色い
- 尿が濃い
- 顔色が悪い
- 便が白灰色
消化器内科でよくみられる疾患
上部消化管
食道裂孔ヘルニア
食道裂孔ヘルニアとは
胃は横隔膜の下に位置しています。この一部(主に胃の入り口である噴門付近)が、何らかの原因で横隔膜(胸腔と腹腔の境にある筋肉)の上に飛び出してしまい、それに伴って、胸やけ、胸痛、胸のつかえを感じるなどの症状が現れるようになります。
主に中年男性や高齢女性に発症しやすく、前者は肥満(主に内臓脂肪の増加)による腹腔内圧の上昇がきっかけと言われています。後者は高齢による筋肉などの脆弱化、骨粗しょう症等による脊椎(背骨)の変形によって起こりやすいです。
これらによって、胃の一部が横隔膜より上に飛び出すと、胃の中に入った食物の逆流を防ぐ働きなどをする下部食道活約筋や横隔膜の締め付けが弱くなって胃液や胃液を含んだ消化物が食道に逆流するようになります(逆流性食道炎の併発)。これが逆流性食道炎を引き起こし、上記の症状がみられるのです。なお逆流性食道炎が起きなければ、無症状のことが多いです。
逆流性食道炎
逆流性食道炎とは
胃液などが食道へ逆流し、それによって食道に炎症が発生している状態を逆流性食道炎(または胃食道逆流症)と言います。主な症状は、胸やけ、ゲップ、胸痛、酸っぱいものが込み上げる(呑酸)、咳(痰が出ない)、物が飲み込みにくい等です。
原因は、高脂肪食・肥満・食道裂孔へルニア・ヘリコバクターピロリ菌未感染などが上げられます。肥満による胃内圧上昇、下部食道活約筋を低下させる喫煙、就寝中の胃酸逆流を増加させる就寝間際の食事などの生活習慣も関与してきます。これらの生活習慣などによって、下部食道活約筋に緩みが起き、機能低下するようになり、胃酸を含む胃液が逆流すると食道は胃粘膜のように酸に耐えられる構造とはなっていない為、食道に炎症を発症し胸やけ等の症状がみられるようになるのです。
バレット食道
バレット食道とは
逆流性食道炎が長期間続くことで、食道粘膜上皮が変性している状態を言います。主に胃に近いとされる食道下部の粘膜で発症します。もともと食道粘膜上皮は扁平上皮なのですが、食道下部の粘膜が炎症を繰り返し引き起こすようになると再生する過程において、粘膜が円柱上皮に変性することがあります。これがバレット食道の発症メカニズムです。
なお、同疾患による特別な症状というのはありません。胸やけや胸痛など逆流性食道炎と同様です。本邦ではまだまれではありますが、特に3cm以上の長さのバレット食道は食道腺がん(食道がん)のリスクになりえます。
食道アカラシア
食道アカラシアとは
食道と胃の間には、胃からの逆流を防ぐための下部食道括約筋と呼ばれる部位があります。この筋肉は、食べ物を食道から胃に運ぶ際に緩むことで円滑に胃へと運ばれるようになります。ここが緩まないためまた食道の蠕動障害により、咀嚼した飲食物が食道から胃の中に通過できなくなる状態を食道アカラシアと言います。
原因に関しては、後天的なアウエルバッハ神経叢の変性あるいは消失と言われています。これが引き金となって下部食道括約筋が緩みにくくなっていきます。主な症状は、長い期間に渡って続くとされる嚥下障害です。またつかえ感、胸痛や食物の逆流などもみられます。
食道カンジダ症
食道カンジダ症とは
カンジダとは真菌の一種で、皮膚や粘膜に常在している菌でもあります。この真菌に食道粘膜が感染している状態を食道カンジダ症と言います。同疾患は、体の免疫力が低下した際に発症しやすいという特徴があります。具体的には、免疫機能低下を引き起こす病気(HIV感染症、悪性腫瘍、糖尿病 等)に罹患している患者さんの日和見感染のほか、免疫力を低下させる薬(ステロイド、抗菌薬 等)の使用がきっかけになることもあります。
よくみられる症状ですが、物を飲み込む際の痛みや飲み込みにくさ、嘔吐・吐き気、喉や胸部付近の違和感などです。人によっては、自覚症状がみられずに内視鏡検査(胃カメラ)をした際に発見されたというケースもあります。
免疫低下があって自覚症状がある場合は、抗真菌薬による投薬治療が行われます。
好酸球性食道炎
好酸球性食道炎とは
好酸球性消化管疾患のひとつです。花粉、カビ、食物などのアレルゲンによってアレルギー反応を引き起こし、好酸球が食道粘膜に浸潤していきます。それによって慢性的な炎症がみられている状態を好酸球性食道炎と言います。主な症状は、口の中にある物を上手く飲み込めなくなる(嚥下障害)、胸やけ、喉がつかえる感じがするなどです。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアとは
胃もたれやみぞおち周辺の痛み等の症状が慢性的に現れているにも関わらず、内視鏡や血液検査などを行っても、器質的な疾患(胃がんや胃潰瘍等)など原因とされる異常が確認できない状態が機能性ディスペプシアです。
発症原因は現時点で特定されていませんが、胃の消化作用や運動機能の低下、などが挙げられています。すなわち、機能性ディスペプシアとは、症状の原因となる明らかな異常がないのに、慢性的に胃がもたれる、みぞおち周辺の痛み、食べてもすぐにお腹が満腹になる(早期膨満感)などの症状を呈する病気を指します。心当たりのある方は、一度当院をご受診ください。
食道乳頭腫
食道乳頭腫とは
主に食道下部に発生する上皮性の良性腫瘍になります。悪性化することは極めてまれです。腫瘍の大きさは大半が1㎝以下で茎のない平坦な形のものが多いです。自覚症状が現れにくいので、内視鏡検査で偶然見つかることがよくあります。発症の原因としては、慢性的に胃から食道へと胃酸や胃酸を含む消化物の逆流による食道粘膜の損傷のほか、ヒトパピローマウイルスの感染も関係しているのではないかと言われていますが現在では否定的とされています。
食道静脈瘤
食道静脈瘤とは
肝硬変等の門脈圧を上昇させる病気(門脈圧亢進症)が原因となって、側副血行路の食道の粘膜下層に存在する静脈が拡張、うっ血するなどして発生する静脈瘤を食道静脈瘤と言います。自覚症状はないですが、破裂を引き起こすと大量出血し重篤な転帰をきたす場合があります。この場合は、生命に影響することもあります。
食道がん
食道がんとは
食道粘膜から発生する悪性腫瘍が食道がんです。食道がんは、大きく扁平上皮がんと腺がんに分けられますが、日本人の食道がん患者さんの9割以上が扁平上皮がんとされ、発症部位としては胸部中部食道が50%程度を占めると言われています。
発症原因ですが、扁平上皮がんでは、喫煙、飲酒、熱い物や辛い物をよく食べるなど、また少量飲酒後に顔が赤くなる方は食道がんになりやすく要注意です。一方の腺がんは、胃酸や胆汁逆流により生じるバレット食道が原因として挙げられます。いずれにしても飲酒や喫煙を好む60~70代の男性に発症しやすいとされ、男性の罹患率は女性の約6倍とも言われています。
主な症状ですが、発症初期は無症状なことが多いです。進行すると、食べ物を飲み込む際に染みる、食べ物のつかえ感、胸痛、嚥下困難を感じるようになります。ちなみに自覚症状が現れる頃は、進行期のがんである可能性が高いです。
胃がん
胃がんとは
胃粘膜で発生する悪性腫瘍のことを胃がんと言います。この粘膜が損傷されることで起きるとされ、最も多い原因がピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)の感染とされています。上記以外では、喫煙、日頃の食生活(塩分の過剰摂取 等)なども挙げられます。
主な症状ですが、発症間もない状態(早期胃がん)では無症状のことが多いです。そのため、定期的に行う胃カメラ(上部消化管)検査によって見つかるケースも多いです。ある程度まで病変が進むと、体重減少、食欲不振、上腹部の不快感、みぞおちの痛み、貧血などの症状が現れるようになります。
治療に関しては、リンパ節転移リスクの低い早期胃がんに対しては、内視鏡治療(EMR内視鏡的粘膜切除術、ESD内視鏡的粘膜下層剥離術)のみで根治可能ですが、転移リスクを有する場合は根治のためリンパ節郭清を伴う外科的切除が必要です。また進行具合によっては術後補助化学療法(抗がん剤)が推奨されます。遠隔転移や多臓器浸潤が強く切除不能な場合は化学療法の適応になります。
胃がんの5年生存率は、ステージ1であれば90%を超えるとされているので、早めに気づいて治療にあたることが大切です。各自治体では、40~50歳以上の方向けに胃がん検診を行っています。対象の方は、定期的に受けられるようにしてください。また、ピロリ菌陽性の場合は、除菌により胃がんリスクは低下しその予防効果は長期にわたり持続するので除菌治療を積極的することを推奨いたします。
尚、国立がん研究センターがん情報サービスによると胃がんは2019年人口動態統計によるがん死亡では第3位でしたが、ピロリ菌感染率の低下や胃がん検診の普及で今後は罹患率・死亡率ともに今後はさらに減少していくものと予想されています。
胃腺腫
胃腺腫とは
胃粘膜の上皮に発生する良性腫瘍のひとつで、高齢者に見られる傾向が多い病変です。通常は、境界が明瞭な白色の丈の低い扁平な隆起を呈することが多いです。自覚症状は基本的には無症状で、胃カメラで偶然に発見されることがほとんどです。胃腺腫はがん化のリスクが高い(胃型)とリスクの低い(腸型)がありますが、見た目だけでリスクを正確に判断することは難しく、また、腺腫の中に一部がんが併存している場合(腺腫内癌といいます)もある為、胃カメラの際、病変の一部を鉗子を用いて採取し病理組織検査に提出します。尚、病理組織検査の結果Goup3の場合(Group1が正常、Group5ががんであり、Group3はその中間)、胃腺腫と診断は確定します。ただし、病変の一部を採取して検査に出すため、病変全体が腺腫なのか一部分にがんが併存しているのかは、この病理診断だけでは確定できないため、病変全体を切除して病理組織検査を行う必要性があります。胃腺腫の一部にがんが併存する可能性も否定できないことから、胃腺腫に対しては基本的には入院の上、早期胃がんに準じた治療(胃カメラを使用し病変を周りの正常粘膜を含めて病変完全に切除)が行われます。
胃アニサキス
胃アニサキスとは
寄生虫の一種であるアニサキスが胃内に入り込むことで発症する病気が胃アニサキスです。アニサキスは長さが2~3㎝程度、半透明乳白色の糸状の形態をしており、主にサバ、イカ、アジ、カツオ、サンマなどに寄生するとされ、これらを生食することが原因とされています。新鮮な魚介類を食べて数時間後(2~8時間後)に激しい胃の痛み(冷汗が出るくらい痛く強弱の波がある)、嘔吐や吐き気が起きます。
これらの症状はアニサキスに対するアレルギー反応であり、アニサキスの虫体を胃カメラで除去することで速やかに症状が消失します。アニサキスが疑われた場合は、当院では緊急に胃カメラで治療可能です。その場合は少なくとも食後6~8時間経過していないと胃の中に食物残渣が残っていてアニサキスを発見し除去することができませんので、食事を摂らずにクリニックに御連絡ください。
尚、アニサキスは、60度以上での1分以上の加熱、マイナス20度以下での24時間以上の冷凍により死滅しますので予防は可能です。
ピロリ菌
ピロリ菌とは
正式名称はヘリコバクター・ピロリ菌と言います。これは胃内に生息するらせん状の細菌で、体長は約1000分の4mmです。そもそも胃の中は強力な胃酸の環境下にあるので、細菌は存在しないと言われていました。その後、研究が進んだことで胃内にピロリ菌の存在が確認されました。さらにこの細菌による感染が胃・十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎、胃がん、胃MALTリンパ腫などと関連があることが判明しました。
ピロリ菌は、胃酸の酸度が低い、あるいは分泌量が少ないとされる幼少時に感染しやすいと言われています。感染経路としては、不衛生な水の飲食利用、ピロリ菌に感染している成人から子どもへの食物の口移しによる経口感染などが指摘されています。また、ピロリ菌感染率が高い世代は、下水道がまだ定着していなかった時期に幼少期を送った50代以降の中高年です。近年、衛生環境が大きく進化したことにより、若年層の感染率は著しく低下しています。
ピロリ菌の感染診断
ピロリ菌の感染有無を調べるには、胃カメラを使う方法と使わない方法があります。胃カメラを使う方法は以下の3種類になります。
検鏡法
採取した組織を染色して顕微鏡で観察する。
培養法
採取した組織を約1週間培養しピロリ菌が増えるかどうか見る。
迅速ウレアーゼ試験
ピロリ菌が持っている酵素が試薬内の尿素を分解してアンモニアを生じるかどうか調べる。
また、胃カメラを使わない方法は以下の3種類になります。
尿素呼気試験
検査用のお薬を服用する前と後に、呼気を採取する精度の高い検査
抗体測定法
血液を採取してピロリ菌に対する抗体の有無を調べる検査
便中抗原測定法
糞便中のピロリ菌抗原の有無を調べる検査
ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌の除菌治療は胃酸の分泌を抑える薬(ボノプラザンまたはプロトンポンプ阻害薬)と 2 種類の抗生物質を1 週朝夕1日2回 服用します。これにより約
92%の方が除菌に成功します。除菌に成功しなかった場合は薬の組み合わせを変えて2 次除菌をすることにより約 98%の方が除菌に成功します。
近年抗菌剤に対して耐性を持つピロリ菌も確認されており、2
次除菌を行っても除菌が成功しない場合は、3次除菌(自費診療)を行うこともできます。
薬を飲んでいる期間は副作用として下痢、軟便、味覚異常、口内炎、カンジダ症、蕁麻疹などが起こる場合がありますが、日常生活に問題ない程度なら
1週間きちんと飲み切っていただくことが除菌成功につながります。
除菌判定
お薬を服用終了後、8週間経過した後に除菌判定します。除菌判定には、尿素呼気試験や便中抗原検査を行います。ただし、胃薬(ボノプラザン、プロトンポンプ阻害薬など)服用している場合は偽陰性(実際は陽性なのに結果が陰性と出る)となり正確な結果が得られない場合があるので少なくとも2週間はこれらの胃薬は休薬する必要性があります。
ピロリ菌除菌後の胃がんリスクは1/3に低下します。除菌成功しても胃がんのリスクは完全に0にはなりません。そのため、除菌後も年に1度定期的に胃カメラを受けることが推奨されています。
急性胃炎
急性胃炎とは
胃炎とは胃の粘膜に炎症が起きている状態を胃炎と言います。胃炎は大きく急性と慢性に分類されます。
急性胃炎とは、胃の粘膜に発赤・浮腫・びらん(胃の粘膜の表面の剥がれ落ちる状態)等が比較的短時間に生じ、急激に上腹部痛・悪心・嘔吐・吐下血などの強い症状が現れる疾患です。原因としては、薬剤の副作用(非ステロイド抗炎症薬:NSAIDs、ステロイド、抗生物質・抗がん剤・等)、喫煙、アルコール、ストレス、胃アニサキス、ピロリ菌などが挙げられます。診断は胃カメラによって行われます。基本的治療は、安静・誘因の除去・薬物療法・食事療法があげられます。初期治療を適切に行う事で短期間で改善される場合が多いです。
慢性胃炎
慢性胃炎とは
慢性胃炎は、胃粘膜が慢性的に炎症を起こしている疾患であり、最も多い原因は、ピロリ菌の感染によるもの(萎縮性胃炎)ですが、ほかにストレスや薬剤の影響、自己免疫(A型胃炎)、食物などのアレルゲン(好酸球性胃炎)、放射線、肉芽腫性疾患(サルコイドーシス・クローン病)、梅毒・結核・寄生虫・ピロリ菌以外のHelicobacter
属(NHPH)で発症する場合もあります。また、ピロリ菌による感染が原因の場合、慢性的に炎症が持続することにより胃の粘膜が萎縮して萎縮性胃炎に進展し、さらに病状が進行すると、腸上皮化生と言って、胃の粘膜が腸の粘膜に似た状態になります。この腸上皮化生の一部ががん化し、胃がんを発症させる恐れがあります。そのため萎縮性胃炎は、前がん病変として捉えられ、胃がん予防のためにも特に胃カメラによる早期発見・早期治療が必須となります。
またピロリ菌感染により、ピロリ菌関連疾患である胃潰瘍・十二指腸潰瘍、胃がん、胃過形成性ポリープ、胃MALTリンパ腫等を発症する場合もあります。
主な症状ですが、無症状の方もいますが、胃もたれ、食欲不振、胃痛、嘔吐・吐き気、腹部の張りなどの様々な症状がみられることもあります。萎縮性胃炎は、上部消化管造影検査(バリウム検査)や胃カメラで診断され、炎症や萎縮の範囲や程度、腸上皮化生の有無を診断します。ピロリ菌感染の診断方法は、培養法・鏡検法・迅速ウレアーゼ試験・抗体測定法・尿素呼気試験・便中抗原法があります。治療は薬物投与によるピロリ菌除菌となりますが、除菌により胃粘膜の炎症は改善しピロリ菌関連疾患の治療や予防につながります。ただし、ピロリ菌除菌成功後も萎縮や腸上皮化生の程度によっては胃がんリスクは継続します。そのため、ピロリ菌除菌成功後も毎年胃カメラをすることが推奨されています。
胃・十二指腸潰瘍
胃・十二指腸潰瘍とは
胃もしくは十二指腸の粘膜に、何らかの原因で粘膜の欠損が生じた病態を胃・十二指腸潰瘍と言います。主に粘膜下層までえぐれていることが確認されると同疾患であると診断されます。発症の原因の大半はピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)の感染とされていますが、非ステロイド抗炎症薬(NSAIDs)や抗凝固薬、低用量アスピリン等抗血小板薬などの薬剤の使用、喫煙、アルコール、ストレスで引き起こされることもあります。
よくみられる症状は、みぞおち周辺の痛み、腹部の膨満感、嘔吐・吐き気のほか、潰瘍からの出血によって、吐血や下血のほか、貧血状態になることもあります。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍が疑われる場合、胃カメラやバリウムを飲んでX線撮影をする検査で潰瘍の有無を確認し、各種方法でピロリ菌感染の有無も確認します。
NSAIDs服用のないピロリ菌陽性潰瘍の場合はピロリ菌除菌治療が第1選択となりますが、その他の場合は主にボノプラザンPCABやプロトンポンプ阻害薬PPIの内服薬で治療となります。尚、合併症(出血、穿孔、狭窄)をきたした場合は内視鏡的止血術や手術など選択されます。
胃ポリープ
ポリープとは
胃ポリープとは、胃の粘膜の表面から発生する良性の限局的に盛り上がっている病変を指します。胃ポリープは主に、胃底腺ポリープ、過形成性ポリープがあります。その大きさは、数㎜程度のものもあれば、2~3㎝まで大きくなるものもあります。また形にしても少し盛り上がっている境界がはっきりしないものから茎があるキノコの形をしたものまで様々あります。そのほとんどは良性と言われています。
胃底腺ポリープは、ピロリ菌に感染してない胃で起きるとされ、がん化の可能性は低いとされています。したがって、数が多い、ポリープが大きいという場合でも経過観察になることが多いです。ただし最近では、まれではありますが、胃底腺ポリープからのがんの発生の報告もあり、ポリープのサイズが大きい場合、粘膜表面に凸凹が目立つ場合は注意が必要です。
過形成性ポリープはピロリ菌に感染した胃の粘膜に発生する赤色調のポリープです。この場合、ピロリ菌を除菌することによりポリープが小さくなる、または消失することもあります。ただし、ポリープが原因で貧血になる場合、また大きさが2㎝以上の場合はがん化する可能性がある為、そのようなケースでは内視鏡治療が検討されることもあります。
カルチノイド
カルチノイドとは
カルチノイド(神経内分泌腫瘍)とは人体に広く分布する神経内分泌細胞(ホルモン等を分泌する細胞)から出来る腫瘍で、多くは胃腸等の上下部消化管、その他膵臓肺等全身の様々な臓器に発症します。その大半が良性とされており、時に悪性のケースもありますがその悪性度は低いとされています。
このカルチノイド(神経内分泌腫瘍)はセロトニン・ヒスタミン・プロスタグランジン等のホルモンを過剰に分泌し、その結果カルチノイド症候群を引き起こすことがあります。カルチノイド症候群では、皮膚の紅潮、動機、下痢、腹痛・嘔吐などの症状が見られます。ただしこのような症状が出るケースは少なく無症状の場合も少なくありません。
カルチノイドの発見のきっかけは胃カメラや大腸カメラで偶然に見つかることがほとんどです。
治療ですが、早期で大きさ1cm以下のものであれば内視鏡での治療が可能ですが、それ以上の大きさや粘膜下に深く浸潤した場合また転移がある場合は外科治療や薬物療法が必要となります。
下部消化管
下痢
下痢とは泥状または水様性の便を頻回に排出する状態のことを言います。正常な便の場合便の水分含有量は75~80%ですが、80%以上の水分量で便の固形状の形態がなくなります。
下痢は2週間以内に治る急性下痢と4週間以上下痢が続く慢性下痢の2つに分類されます。急性下痢の8割は感染性(細菌・ウイルス・真菌・原虫)です。細菌性はカンピロバクター腸炎、サルモネラ腸炎、病原性大腸菌O-157、エルシニア腸炎、黄色ブドウ球菌、細菌性赤痢、腸結核などが挙げられます。また、感染性でなければ薬剤性腸炎があげられ、抗菌薬起因性腸炎(偽膜性腸炎、出血性腸炎、MRSA腸炎)のほか、低用量アスピリン腸炎やNSAIDs起因性腸炎や免疫チェックポイント阻害薬腸炎、などがあります。その他の原因には、食生活の乱れ(食べ過ぎや飲みすぎ)や乳糖不耐症(乳製品を摂ると下痢・腹痛など生じる)などもあります。慢性下痢は、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病、ベーチェット病)、collagenous
colitis、Zollinger-Ellison症候群、carcinoid症候群、吸収不良症候群、慢性膵炎、甲状腺機能亢進症、過敏性腸症候群などがあります。急性下痢の場合は対処療法で軽快する場合が多いですが、慢性下痢は原因疾患により治療法が異なります。急性下痢で、発熱や血便、腹痛の増強、激しい下痢、頻回の嘔吐、脱水がある場合、また、4週間以上下痢が継続する場合(慢性下痢の場合)は病気が隠れている可能性もあるため受診することをお勧めします。
便秘
便秘とは便通異常のひとつに数えられ、体外へと排出する糞便の量が十分ではなく、気持ちの良い状態で排出できていない場合を便秘と言います。なお便秘症が6ヵ月以上続き、少なくとも最近の3か月間で排便回数が週3回未満、かつまたは怒責、硬便、残便感などの排便困難症状が少なくとも4回に1回以上の頻度、などの条件が2項目以上満たし、過敏性腸症候群が除外されていると慢性便秘症と診断されます。便秘症は非常によく見られる疾患ですが、60歳までは女性のほうが多いものの60歳以降は男女差がなくなり、年齢とともに有症率が高くなります。
便秘の原因については、大きく器質性と機能性に分けられます。前者は主に病気に伴って起きる便秘です。大腸が狭窄すること(大腸がん、クローン病 等)もあれば、排便回数の減少(大腸が大きく膨らむ巨大結腸症
等)、腸の形態変化による排便困難(直腸瘤、巨大直腸 等)などのケースがあります。後者は、直接的な原因とされる病変が見当たらない便秘になります。この場合、大腸で便が通過するのが遅い(薬剤や代謝・内分泌疾患の影響
等)、普段の食生活による影響(食物繊維の不足、食事の摂取量が十分でない
等)で排便回数や量が不足している、硬い便による排便困難(過敏性腸症候群の便秘型)などが挙げられます。
便秘の場合は、器質的疾患の有無の確認をするため大腸内視鏡検査施行する必要性があります。そのうえで機能的便秘症の場合の治療は、食事や水分摂取、運動などの生活習慣の改善が基本であり、排便コントロールが不良な場合は薬物療法での治療が必要になります。薬物療法は、基本は酸化マグネシウムが第一選択となりますが、効果不十分な場合は刺激性下剤(アントラキノン系薬剤やジフェニール系薬剤)や新規便秘薬(ルビプロストン・ナルデメジン・リナクロチド・エロビキシバット・ポリエチレングリコール・ラクツロース)への変更が検討されます。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群とは
腹痛、下痢、便秘などの消化器症状を訴えるものの、検査をしても明らかな病変などの異常がみられず、上記の症状を慢性的に繰り返している状態が過敏性腸症候群です。便通異常により、下痢型・便秘型・混合型(下痢と便秘を繰り返す)・分類不能型の4つの型に分けられます。なお消化器症状以外にも頭痛やめまいなどの自律神経症状、不眠やうつ等の精神症状が現れることもあります。多くの場合、排便をすることで症状が軽快するようになります。
同疾患は20~40代の世代の患者さんが多く、日本人の1割程度の方が発症しているとも言われています。発症の原因に関しては、明確には特定できていません。ただストレスやプレッシャーなどが自律神経に作用し、それが腸の運動に影響することで便通異常が起きると考えられています。感染性腸炎の回復後に発症しやすいことも知られています。治療法ですが、生活改善を行っても症状が改善しない場合や症状が強い場合には薬物療法が行われます。
感染性腸炎
感染性腸炎とは
何らかの病原微生物(細菌、ウイルス、寄生虫、原虫)が腸内へと侵入、あるいは粘膜に感染するなどして発症する病気が感染性腸炎です。細菌による急性下痢症は夏季に多く発生し、頻度の高いものはカンピロバクター、サルモネラ、病原性大腸菌の順です。ウイルスによる急性下痢症は冬期に多く、ノロウイルスやロタウイルスの順に発生します。
主な症状は、嘔吐や下痢、腹痛、発熱などで、組織障害が強い場合は血便を伴います。カンピロバクター腸炎は汚染された水・食物、特に鶏肉が原因のことが多く、潜伏期間は2-7日です。サルモネラ腸炎は主に鶏卵やその加工食品が原因の場合が多いです。潜伏期は8~48時間と短く38.5度以上の発熱、激しい下痢をきたす場合が多いです。腸管出血性大腸菌腸炎の代表的な型はO157であり、生の牛肉やレバーで集団感染を来す場合があります。潜伏期間は4―8日、軽症例は1週間で軽快しますが、溶血性尿毒症症候群(溶血性貧血・血小板減少・急性腎障害)を併発し重症化する場合もあります。ノロウイルス腸炎は生牡蠣や二枚貝が原因となる場合が多いです。吐物や便を介して人から人に感染し家族内発生が高率です。潜伏期間は12-48時間で突然の下痢・嘔吐をきたします。消毒には次亜塩素酸が有効です。
急性腸炎の場合はほとんどが自然軽快しますが、下痢や嘔吐に伴う脱水症状がある場合は経口補水剤や静脈的点滴、細菌性腸炎が考えられ状況によっては抗生剤治療を開始する場合もあります。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎とは
大腸の粘膜が何らかの原因によって炎症が生じ、“びらん”や“潰瘍”といった病変が形成される原因不明の非特異性大腸炎を潰瘍性大腸炎と言います。発症原因は現時点で特定されていませんが、免疫反応の異常が関係していると言われています。
主な症状は、血が混じっている便(粘血便)、下痢、腹痛ですが、重症化すると発熱や体重減少を生じます。尚、潰瘍性大腸炎には、炎症が起きて症状が強く現れる活動期と、症状が治まっている寛解期があります。治療をしっかり継続すれば多くの方は寛解を維持することができますが、人によっては再燃(寛解期から再び活動期になってしまうこと)して、活動期と寛解期を繰り返してしまうこともあります。なお炎症の程度は粘膜下層までに限局するとされ、炎症の範囲は直腸に限局することもあれば、大腸全体に及ぶこともあります。その範囲によって4つのタイプ(全大腸炎型、左側大腸炎型、直腸炎型、右側あるいは区域性大腸炎)に分類されています。ちなみに炎症の範囲は、広がることもあれば、狭まることもあります。なお炎症範囲が広がるほど重症化しやすいとされています。さらに潰瘍性大腸炎の症状には、腸管以外の部位で起こる腸管外合併症があり、皮膚症状・関節症状などをきたす場合もあります。治療の基本は、5-アミノサリチル酸(5^ASA)製剤の内服ですが、効果が不十分の場合はステロイドや免疫調整剤、分子標的治療薬などの投与が必要な時もあります。重症例では手術も考慮されます。
クローン病
クローン病とは
潰瘍性大腸炎と同様に炎症性腸疾患のひとつで、主に小腸や大腸などの粘膜に炎症が起きることで、腸管の粘膜にびらん(粘膜がただれている状態)や潰瘍(粘膜がえぐられている状態)ができる原因不明の慢性の病気です。遺伝的要因と環境要因が組み合わさるなどして、腸粘膜に免疫異常が起きることで発症すると言われています。10代後半~20代の若い世代に発症しやすいとされ、男女比では2:1と男性患者さんが多いのも特徴です。
なおクローン病に関しては、潰瘍性大腸炎のように大腸にのみ炎症がみられるというわけではありません。口から肛門まで1本の長い管でつながっている消化管のどの部位にでも発症する可能性があります。ただ同疾患の多くは大腸もしくは小腸を中心に炎症・潰瘍を認める事が多く、病状が悪化すると腸管狭窄(腸管が狭くなる)や瘻孔(腸管に孔があいて腸管と腸管、または腸管と他臓器がつながる)を生じることがあります。
主な症状は、腹痛、下痢などの消化管症状と発熱、体重減少、栄養障害などの全身症状です。また、肛門周囲膿瘍や痔瘻等の肛門疾患などの病気が併発、関節炎・皮膚病変などの合併症をきたす場合もあります。
根治治療はありませんが、十分な治療により予後が改善されますが、症状が落ち着いている状態(寛解期)になっても症状が悪化(再燃)する場合もあるので、長期にわたってしっかりと治療することが重要です。
治療方法は、炎症が起きている部位の刺激を避けるため、絶食して点滴または成分栄養剤を経口または鼻から投与するまたは、5-アミノサリチル酸(5^ASA)製剤、ステロイドや免疫調整剤、生物学的製剤などの薬物治療をおこないます。
ベーチェット病
ベーチェット病とは
ベーチェット病は、原因不明の全身性炎症性疾患で、口内炎(口腔内アフタ性潰瘍)、外陰部潰瘍、皮膚病変(結節性紅斑)、目が見えにくいなどの眼症状(ぶどう膜炎)の4徴が特徴の疾患です。消化管病変が症状の中心となるのが腸管ベーチェット病と言い、回盲部に深掘れ潰瘍を形成することが多いです。
尚、腸管ベーチェット病では、食道から直腸の間にかけて全消化管にも潰瘍性病変を形成することもあり、腹部腫瘤を認める場合もあります。主な症状は、腹痛・発熱・下痢・血便です。治療は5-アミノサリチル散(5ASA)製剤、サラゾスルファピリジン(SASP)等投与されますが、症状が強い場合はステロイド、チオプリン製剤、抗TNF-α抗体製剤が用いられます。腸管が穿孔(穴が開く)や大量出血した場合は手術が必要となる場合があります。
腸結核
腸結核とは
腸結核は腸に結核菌が感染することで起きる病気です。好発部位は小腸の終末回腸から上行結腸です。主な症状は腹痛、下痢、下血、発熱、倦怠感、体重減少などですが、無症状で大腸内視鏡検査で偶然発見されるケースも近年増加しています。治療は、活動期肺結核の治療に準じた抗結核化学療法を行います。最近では、高齢者や薬剤(抗がん剤、生物学的製剤、免疫抑制薬)を使用することにより免疫機能が抑制され発症するリスクが増加すると懸念されています。
虚血性大腸炎
虚血性大腸炎とは
虚血性大腸炎は、大腸粘膜の血流障害によって生じた大腸の可逆的な区域性炎症と定義し、現在では狭窄型と一過性型の2型に分類されます。
ます。60歳代以上の便秘気味の女性に好発しやすいですが、若い世代に見られることもあります。突発する腹痛、下痢、血便が主な症状です。また左側の結腸部分で発症しやすいため、腹痛は左下腹部に生じることが多いです。発症の原因については、動脈硬化や便秘による腸管内圧の上昇などが挙げられます。高血圧や糖尿病、脂質代謝異常症などの病気を有する患者さんに多く、腸管の蠕動運動が亢進や力みなどの腸管内圧の上昇などが複雑に絡み合って発症します。
本症は自然治癒傾向が強く、約90%は一過性型の経過をたどるため基本的には経過観察のみでよいですが、狭窄型では治癒が遷延することが多く腸管が高度に狭くなった場合は内視鏡的拡張術や外科的手術等が検討されます。
大腸がん
大腸がんとは
大腸の粘膜に発生した悪性腫瘍のことを大腸がんと言います。この場合、盲腸、結腸、直腸、肛門で起きるがんのことを指しますが、発症しやすい部位は直腸とS状結腸です。なお大腸がんは、良性のポリープである腺腫の一部からがん化することもあれば、大腸粘膜より直接発生することもあります。
発症初期は無症状ですが、病状が進行すると血便、腹痛のほか、便通異常(下痢と便秘)を繰り返すようになります。早期(ステージ0もしくは1)に発症に気づいて治療することができれば、5年生存率は90%以上となっています。大腸がんは、50歳を過ぎる頃から罹患率が高くなるので、これまで何の症状がなかったという方も50歳を迎えたら大腸内視鏡を受けるようにしてください。可能なら40歳を過ぎたら一度は大腸内視鏡検査を受けることをお勧めします。
当院では、大腸内視鏡は全て拡大内視鏡を完備しており、病変に特殊な光を当てて画像強調拡大観察(NBI)や色素を散布し拡大観察(pit
pattern診断)することで、的確な診断をし、その病変が内視鏡切除が必要か外科手術が必要か経過観察して良い病変か治療方針を決定することができます。
治療ですが、早期大腸がんの一部は内視鏡治療で完治できます。
早期大腸がんはがんの浸潤が粘膜下層までにとどまっているがんであり、粘膜内がんと粘膜下層浸潤がんに分けられます。粘膜内がんはリンパ節転移のリスクが無いため内視鏡切除で完治できます。粘膜下層浸潤がんはリンパ節転移リスクがありますが、病理検査で転移リスクを詳細に検索でき、リンパ節転移のリスクが低い場合は内視鏡治療で経過観察可能です。リンパ節転移リスクがある場合は手術による追加治療が必要になります。
内視鏡治療は、EMR(内視鏡的粘膜切除術)またはESD(内視鏡的粘膜下層切除術)などが選択されます。
なお大腸がん発症の原因については完全に解明されているわけではありません。ただリスク要因として、環境要因(食生活の欧米化
等)、遺伝的要因(家族性大腸腺腫症 等)のほか、長期に渡る潰瘍性大腸炎からの併発というケースもあります。
大腸ポリープ
大腸ポリープとは
周囲の大腸粘膜よりも内腔側に隆起したものを大腸ポリープと言います。40歳以降の方にみられ、直腸やS状結腸できやすいといわれ,ポリープの大きさは数mmの小さなものから20mmに及ぶものまでまちまちです。
大腸ポリープの主な症状ですが、ポリープを発症しても無症状の場合がほとんどです。そのため、ポリープを早期に発見・治療するには、大腸内視鏡検査を受けることが重要となります。ただポリープが大きければ大腸内で出血し血便が出たり、あるいは腸閉塞を引き起こすことがあります。
大腸ポリープは、腫瘍性と非腫瘍性に分けられます。上皮性腫瘍性では、悪性(早期がん)と良性(腺腫)に分けられます。非上皮性腫瘍は、平滑筋性腫瘍、脂肪腫などがあります。非腫瘍性では、炎症性ポリープ、過形成性ポリープ、過誤腫性ポリープなどがあります。
腫瘍性ポリープでは、腺腫は大腸ポリープの中では最多(80%)の良性のポリープですが、大きさが増すにつれがん化する確率が高くなります。米国National
Polyp
Studyより、腺腫の内視鏡切除により大腸がんは76~90%抑制可能であり、53%の死亡率抑制が得られると報告され、日本においても積極的に腫瘍性ポリープの内視鏡切除(内視鏡的ポリープ切除術【ホット・コールド】、内視鏡的粘膜切除術EMR、内視鏡的粘膜下層剥離ESD)が広く行われています。また、特に腫瘍性ポリープの内視鏡治療を行った場合は3年以内に大腸内視鏡を施行することが推奨されています。尚、非腫瘍性ポリープのほとんどはがん化する心配はないといわれています。
腸閉塞
腸閉塞とは
腸閉塞とは、さまざまな原因によって腸管内の消化液や摂取した食物の通過が障害された状態のことを言います。通過障害により、腹痛、おなかが張る、吐き気、嘔吐、排ガスや排便の停止などの症状が生じます。
腸閉塞は、機械的腸閉塞と機能的腸閉塞に大きく分けられます。前者は、物理的に腸管が閉塞する単純性と血流障害も併せて発生する複雑性(絞扼性)に分けられます。なお現在は、機械的腸閉塞のことを腸閉塞、機能的腸閉塞(腸管麻痺)のことをイレウスと表記されるようになっています。
発症の原因ですが、単純性では、これまでの開腹手術や炎症(大腸憩室炎 等)による癒着、大腸がんをはじめ、ポリープやクローン病などによる閉塞によって引き起こされます。複雑性の原因としては、索状物等によって腸が締め付けられる、腸軸捻転症、嵌頓ヘルニア、腸重積症などが挙げられます。機能的腸閉塞(イレウス)に関しては、腹膜炎や開腹手術後、薬剤などによって引き起こされます。
単純性腸閉塞や機能的腸閉塞は絶飲食、点滴を腸管内減圧(鼻から胃管やイレウス管を胃内または十二指腸奥まで入れる)で症状が改善されることが大半です。複雑性腸閉塞は腸管や腸管膜の血流障害を来し腸管壊死、さらには敗血症(細菌感染することにより体の重要な臓器の機能が障害を引き起こす病気)を引き起こし命の危険性を来す為緊急手術が必要になる事が多いです。
大腸憩室症(憩室炎、憩室出血)
大腸憩室症とは
大腸の内壁が外側の方向に飛び出し、袋状に膨らんでいる状態を大腸憩室症と言います。これは加齢と共に増加し40歳以上の中高年者に多く多発しやすいとされています。便秘等による大腸内の圧力の上昇、加齢による腸管壁の脆弱化などが原因とされていますが、食物繊維の摂取が不足している人にもできやすいともいわれています。
主な症状ですが、大腸憩室症のみでは症状が現れることはありませんが、憩室内に血管が破綻出血して大腸憩室出血を起こすと、腹痛をきたさないで大量の血便を生じます。また、腸管の内圧が便秘などで高くなり憩室にも便が入り込み、そこで細菌が増殖して炎症を起こすとなると大腸憩室炎を生じ腹痛や発熱をきたします。大腸憩室出血や大腸憩室炎をきたした場合には早急な治療が必要となります。
大腸憩室出血は造影CT・大腸内視鏡で診断されますが、出血は自然に止血することもあれば、内視鏡を用いて止血することもあります(バンド結紮法・クリッピング
等)。内視鏡止血術が困難な場合は血管内治療(動脈塞栓術)や手術行う場合もあります。
大腸憩室炎は腹部CTなど画像診断が有効ですが、症状が軽快した後大腸内視鏡施行し、大腸がんその他疾患を除外診断した上で、腸管に炎症憩室を認めるあるいは憩室の存在確認が可能であれば大腸憩室炎と診断できます。治療は、炎症による膿瘍(膿みのかたまり)
や穿孔(腸管に穴があく)が伴わなければ内科的に治療(抗生剤の投与)となります。ただし内科的な治療が困難な場合や穿孔や膿瘍を形成している場合は、外科的手術や膿瘍ドレナージといった追加治療が必要になります。
大腸カルチノイド
大腸カルチノイドとは
大腸の中でも直腸で発生することが多いので直腸カルチノイドとも呼ばれます。そもそもカルチノイドとは、神経内分泌腫瘍(神経内分泌細胞より発生する腫瘍)のひとつで、悪性度が低いとされるものになります。自覚症状が出にくいので、内視鏡検査によって偶然発見されることが多いです。その際にその腫瘍が1㎝以下で浸潤が粘膜下層までなら内視鏡で切除します。内視鏡切除はESMR-LやEMR-Cといった通常のEMR内視鏡的粘膜切除術に工夫を加えた手技が推奨されています。尚、深部への浸潤やリンパ節転移が疑われる場合に手術治療を行います。
虫垂炎
虫垂炎とは
虫垂は盲腸にぶら下がっているような部位のことを言います。一般的には盲腸あるいは盲腸炎と呼ばれますが、実際は盲腸ではなく、虫垂の炎症なので虫垂炎が正しいです。
発症原因ですが、虫垂になんらかの閉塞を生じ、虫垂内腔からの分泌液の流出障害を来し、その結果、分泌液貯留によって腫大した虫垂になんらかの細菌などの感染きたすことで、虫垂炎が生じます。原因は細菌やウイルスなどの病原体に感染や糞石によることが多いです。典型的な症状は胃のあたりの痛みからはじまり、その後半日~2日以内に虫垂のある右下腹部に痛みがうつります。その他、吐き気や嘔吐や発熱をきたします。腹部CTなど画像診断で虫垂炎は診断可能です。治療法は、抗生剤を用いた内科的な治療と手術がありますが、抗生剤での治療を開始しても改善されなければ手術が必要となります。抗生剤治療で軽快しても30%ほどの再発率があり、後に手術が考慮される場合もあります。
肛門疾患
いぼ痔
いぼ痔とは
正式には痔核と呼ばれます。痔核は、肛門クッション(肛門を締める筋肉である肛門括約筋と粘膜や皮膚との間にある、結合組織や筋組織、動脈や静脈の血管が網の目のように集まった部分のこと)が、排便時にうっ血することで起きるもので、見た目はこぶ状のようになっています。なお痔核に関しては、大きく内痔核と外痔核に分けられます。
原因としては、便秘、排便時に強くあるいは長くいきむ、長時間座りっぱなしのままでいること、腹圧のかかる作業などをよくしている、アルコールの過剰摂取、冷え、妊娠や出産時も起きやすいとされています。
尚、内痔核は歯状線(直腸と肛門の境目)の内側(直腸側)に発生する痔核になります。一方外痔核は歯状線の外側に発生する痔核です。
内痔核は痛みを感じることはありませんが、症状が進むと徐々に痔核(いぼ)が大きくなり、肛門の外側に飛び出していきます。脱出の程度によって、Ⅰ度~Ⅳ度に分かれており(1度:脱出はないが出血する。2度:排便時に脱出するが排便後すぐ元に戻る。3度:排便時に脱出し指で押し込まないと戻らなくなる。4度:常に脱出したままである。)、1度と2度は保存療法(生活習慣改善や座剤処方)で対応となりますが、3度以上では手術が必要になります。尚、脱出した内痔核が絞扼されて循環障害と著明なむくみをきたした場合は嵌頓痔核と言います。
外痔核の中でも、歯状線より外側にある肛門クッションの血管に血栓(血のかたまり)ができたものを、血栓性外痔核といいます。血栓性外痔核の特徴的な症状として挙げられるのが、強い痛みです。血栓性外痔核の治療法は、軟膏や内服薬となります。
切れ痔
切れ痔とは
排便をする際に肛門の皮膚が裂けたり、切れるなどして出血している状態を一般的には切れ痔と言います。正式な病名は裂肛です。原因としては、硬い便が出る、勢いのある下痢をする等によって起きるとされています。便秘をよくする方に発症しやすく、若い女性の患者さんがよく見受けられます。主な症状は、排便時などに起きる強い痛み、皮膚が裂けたことによる出血ですが、出血は内痔核に比べたら軽度です。治療は食事習慣や排便習慣などの生活習慣の見直しをし、水分や食物繊維を十分に摂取し、正しい排便習慣を身に着けるようにした上で、軟膏などの外用薬や緩下剤などで便秘の改善を促します。
なお切れ痔は慢性的に繰り返すと裂傷は潰瘍化し瘢痕化し肛門が狭くなったり、ポリープが形成されたりすることもあります。このような場合は、手術が必要となります。
痔瘻(あな痔)
痔瘻とは
肛門管内の歯状線の小さなくぼみ(肛門陰窩)に細菌(大腸菌
等)が入って、肛門括約筋間の肛門腺で感染が起きる事を肛門周囲膿瘍と言います。(1次口)やがてこの膿は、どんどんたまっていき、やがて皮膚側に排膿して開通したトンネルのような穴(瘻管)が形成されてしまうようになります(2次口)。これを痔瘻と言います。
慢性的な下痢による肛門内部の粘膜への刺激が原因と考えられていますが、腸に慢性的な炎症を引き起こすクローン病によって引き起こされることもあります。
肛門周囲膿瘍も含めた主な症状ですが、化膿による痛みや腫れのほか、発熱がみられることもあります。瘻管が作られると(二次口から)膿が排出されていきます。痔瘻になると痛みや出血は少ないですが、膿は出続けることになります。
痔瘻の初期急性期病変の肛門周囲膿瘍の治療は排膿切開ですが、痔瘻が形成された場合は手術による治療が必要となります。
肝・胆のう・胆道疾患
脂肪肝 NAFLD/NASH
脂肪肝とは
肝臓に脂肪が必要以上に蓄積されている状態を脂肪肝と言います。具体的には肝細胞に5%以上の脂肪が溜まっていると確認された場合としています。
肝臓に脂肪が多く蓄積した状態が脂肪肝です。脂肪肝は大きく、アルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)に分けられます。前者は、アルコールの過剰摂取が原因で発症する脂肪肝です。後者は、お酒以外の原因で肝細胞に脂肪が蓄積している状態です。原因としては肥満、2型糖尿病、脂質異常症などが挙げられます。NAFLDはさらに非アルコール性脂肪肝(NAFL)とNAFLDが炎症と線維化を伴い肝硬変や肝がんに進展する可能性のある非アルコール性脂肪肝炎(NASH、NAFLD患者さんの10~20%)に分けられます。
主な症状ですが、ある程度まで病状が進行しないと現れにくいです。そのため早期発見するためには、定期的に健康診断を受け、腹部超音波や腹部CTによる画像診断や血液検査をすることが必要です。
NAFLD/NASHは内臓肥満を主病因としている為、食事や運動によるダイエットが第1の治療法となります。その他基礎疾患として、2型糖尿病・脂質異常症・高血圧がある場合は各々の内服治療を継続することも必要ですが、これら基礎疾患がない場合はビタミンE投与も有効です。
尚、最近では従来のNAFLD、NASHはメタボリック症候群の基準の一部を満たす場合に限定して、metabolic dysfunction associated steatotic liver disease(MASLD)、metabolic dysfunction associated steatohepatitis(MASH)と診断することに変更なりました。
急性肝炎
急性肝炎とは
肝細胞が短期間で破壊され肝機能障害を呈する疾患を急性肝炎と言います。原因としては、ウイルス性、自己免疫性、薬物性、アルコール性があります。ウイルス性では、A型、B型、C型、D型、E型の5種類がありますが、上記以外にEBウイルス、サイトメガロウイルス等のウイルスが原因の場合もあります。主な症状は、全身の倦怠感、黄疸(白目の部分や皮膚が黄色っぽくなる)、発熱、嘔吐・吐き気、食欲不振などです。
ウイルスが原因の急性肝炎の場合は安静のみで自然寛解・治癒することが多く、安静に過ごすことで治癒していきます。ただ、ごくまれに肝障害が著しく悪化し重篤化することがあります。これを劇症肝炎と言います。この場合、肝性脳症と呼ばれる意識障害などがみられます。
慢性肝炎
慢性肝炎とは
肝臓(肝細胞)に炎症が発生し、その状態が6ヵ月以上持続していると慢性肝炎と診断されます。原因の大半は、C型肝炎ウイルスとB型肝炎ウイルスの感染によるものです(感染経路は、輸血、注射器の使い回し、針刺し事故、入れ墨を彫る 等)。ちなみに慢性肝炎の患者さんの7割以上がC型、2割程度がB型です。上記以外では、薬物性肝障害、自己免疫性肝炎、アルコール性、非アルコール性脂肪性肝疾患が原因の場合もあります。
主な症状ですが、慢性ウイルス性肝炎では、全身の倦怠感が数ヵ月続く、食欲の低下のほか、トランスアミナーゼ(AST、ALT)の上昇が半年以上続いているなどです。この状態を長く続けると、肝硬変や肝がんの発症リスクを上昇させるので注意が必要です。
肝硬変
肝硬変とは
肝臓の慢性的な炎症によって、肝細胞では破壊と再生のサイクルが続くようになります。これが同細胞を減少させ、肝臓は線維化されるようになります。この繰り返しで肝臓が硬くなってしまい、肝機能が著しく低下している状態が肝硬変です。
発症の原因については、ウイルス性肝炎(C型もしくはB型)、アルコール性肝障害、NASH(非アルコール性脂肪肝炎)、自己免疫性などによるものですが、最も多いのはC型肝炎がきっかけの肝硬変です。
主な症状ですが、線維化が進む中でも肝機能が損なわれていない代償期であれば、症状が現れにくいとされています。ただ人によっては、倦怠感や食欲不振などがみられます。さらに肝硬変が進行し、肝機能の低下が現れる頃(非代償期)になると、黄疸、肝性脳症(意識障害)、腹水による腹部の膨満感、手足のむくみ(浮腫)、胃・食道での静脈瘤・脾腫(脾臓の腫れ)・血が止まりにくいなどの症状が生じます。
なお肝硬変は、成因にかかわらず、肝細胞がんを発症させやすくする病気であることも知られています。
肝臓がん
肝臓がんとは
肝臓に発生したがんを総称して肝臓がんと呼びます。肝臓がんは、大きく原発性肝がんと転移性肝がんに分けられます。原発性肝がんの種類は、発症する細胞から、肝細胞がん、肝内胆管がん、その他のがんに分類されます。中でも肝細胞がんが95%と最多です。肝細胞がんの大きな成因は、C型肝炎ウイルスとB型肝炎ウイルスの持続感染による慢性肝炎・肝硬変ですが、最近では非アルコール性脂肪肝炎(NAFLD)脂肪肝からの発症も増えてきています。原発性肝がんは、60歳以上の方に発症しやすく、男女比では男性の患者さんの方が多いです。自覚症状ですが、発生間もない頃は自覚症状がみられません、進行することで黄疸や腹水・腹部にしこり、張り、痛みなどが出ます。
肝内胆管がんは、肝内胆管の上皮から発生するがんで、大半は腺がんです。発症の原因に関しては、肝硬変・B型肝炎・C型肝炎・非アルコール性脂肪肝炎・糖尿病・肥満・飲酒・喫煙・肝内結石、原発性硬化性胆管炎、膵胆管合流異常症などが挙げられます。主な症状ですが、自覚症状は出にくいとされています。その後、ある程度進行することで、黄疸、肌のかゆみ、だるいなどの症状が現れるほか、腹痛や食欲不振などもみられます。
転移性肝がんは、他の臓器の悪性腫瘍が転移して発生する肝臓がんになります。消化器がん(胃がん、大腸がん、膵がん、胆道がんなど)が原因として最も多いです。主な症状ですが、無症状のこともあれば、元々発生している部位の症状が現れることもあります。そのほか、進行に伴い黄疸、食欲不振、腹水、腹痛、腹部の膨満感などの症状もみられます。
胆嚢結石
胆嚢結石とは
胆嚢の中で発生した結石のことを胆嚢結石と言います。肝臓で胆汁という消化液が作られていますが、この胆汁液は肝臓から送り出されて胆嚢内に蓄積されます。この胆汁液はコレステロール・胆汁酸・ビリルビンという胆汁色素等でできていますが、これらの成分のバランスが崩れ胆嚢内に胆石が出来ると言われています。尚、胆嚢結石の大部分はコレステロール結石です。加齢、女性、中年期以上の肥満の方などに起こりやすいと言われています。
胆嚢結石の有症状率は20%ほどであり、多くは無症状で経過します。一方油っこいものを食べた後、胆嚢が収縮すると胆石が胆嚢の出口につまり、食後に肋骨の右側下あたりが激しく痛むようになりますが、これを胆石発作と言います。この状態が長く続くと、細菌感染が併発し、急性胆嚢炎となり、発熱・黄疸(皮膚が黄色くなる)・上腹部痛が伴います。
胆嚢結石は、無症状であれば経過観察、有症状であれば腹腔鏡下胆嚢摘出術が基本ですが、胆嚢炎を併発している場合はその重症度にあわせて治療方針を決めます。初期治療(絶食・補液・抗生剤投与)後、急性胆嚢炎が中等症以上の場合は胆嚢ドレナージ(うっ滞している胆管の胆汁を体外に排出させる)した後に腹腔鏡下胆嚢摘出術が進められます。
総胆管結石
総胆管結石とは
総胆管と呼ばれる部位で発生した結石(胆汁液の成分が固まって結石になる)、もしくは胆嚢にできた結石が総胆管に落下してきた結石のことを総胆管結石と言います。この場合、コレステロール結石ではなく、ビリルビンカルシウム結石が多いです。
総胆管結石の有症状率は90%以上であり、結石が総胆管にはまり込むと右上腹部痛を生じます。総胆管の出口に結石がはまり込んで細菌感染を伴うと急性胆管炎となり、発熱、黄疸(皮膚が黄色くなる)、上腹部痛を認めます。さらに悪化すると細菌が血液中に入り込み敗血症を発症し、意識障害、ショックを伴うことがあります。総胆管の出口である十二指腸乳頭部を結石が塞ぎ込むと急性膵炎を引き起こすこともあります。総胆管結石症は胆石膵炎や胆嚢結石を併発しているかどうかで、急性膵炎の治療、内視鏡的胆管結石除去術または内視鏡的ドレナージ(うっ滞している胆管の胆汁を体外に排出させる)、胆嚢摘出術等治療が行われます。
胆嚢ポリープ
胆嚢ポリープとは
胆嚢の粘膜に発生する突起物が胆嚢ポリープです。近年、食生活の欧米化にともない増加していると言われています。
同ポリープの大半は良性のコレステロールポリープで、多くは数㎜程度です。何らかの自覚症状がみられることはありません。そのため、健康診断での超音波検査等によって発見されて気づくことがよくあります。上記ポリープであればで、ほとんどが癌化しませんので治療は不要です。ただ10mm以上でさらに大きくなる可能性がある、さらに大きさに関係なく、ポリープの形が幅広い、大きさが増大する場合は、がんも考えられるので外科的治療となります。
急性胆嚢炎
急性胆嚢炎とは
急性胆嚢炎とは胆嚢に炎症が生じた状態を言います。そのほとんどは胆嚢結石が原因と言われています。発症の流れですが、胆嚢結石が落下し、胆嚢と胆管をつないでいる胆嚢管が詰まるようになると、胆汁が流れにくくなります。これが結果的に細菌感染(原因菌は大腸菌 等)を引き起こし、急性胆嚢炎となります。主な症状は、上腹部痛(みぞおちや右の脇腹あたり)、嘔吐・吐き気、発熱、などです。なお炎症が進行すると、胆嚢穿孔(胆嚢に孔が開く)が起きることもあります。このほか重篤化すると、急性腹膜炎、胆嚢周囲膿瘍などを併発することもあります。
重症度により治療は行われますが、初期治療(絶食・補液・抗生剤投与)の後、胆嚢摘出術が行われますが、中等症以上で緊急で手術や胆嚢ドレナージ(うっ滞している胆管の胆汁を体外に排出させる)、重症度により症状が軽快してから待機的に手術する場合もあります。
急性胆管炎
急性胆管炎とは
胆管で発症する炎症性疾患になります。この場合、総胆管結石や悪性腫瘍等によって胆管が閉塞するなどして胆汁がうっ滞すると、やがて胆管に細菌感染(原因菌は大腸菌 等)が起きます。これによって発症するのが急性胆管炎です。主な症状は、発熱、黄疸、腹痛(右上腹部の痛み)です。なお細菌などを含んだ胆汁が肝臓へと逆流し、血液中にまで含まれてしまうと敗血症等を引き起こし、ショック症状や意識障害などの症状が現れることもあります。 初期治療は、絶食・補液・抗生剤投与ですが、これに加えて胆道ドレナージ(うっ滞している胆管の胆汁を体外に排出させる)を行います。
胆嚢腺筋症
胆嚢腺筋症とは
胆嚢壁が部分的もしくは全体的に分厚くなってしまう病気のことを胆嚢腺筋症と言います。原因は胆嚢内圧の上昇など説もありますが明らかな原因は不明です。同疾患は、大きく3つのタイプ(底部限局型、分節型、びまん型)に分けられます。底部限局型は、胆嚢の一部(底部)に限定的に胆嚢壁が肥厚します。分節型は、胆嚢の体部や頸部を中心に胆嚢壁が全周性に肥厚化します。びまん型は、胆嚢壁全体が肥厚化します。
主な症状ですが、無症状のことがほとんどです。そのため、健康診断などでの超音波検査で偶然見つかることもあります。胆嚢癌を疑う所見がなければ治療は必要ないですが、経過観察(定期的な超音波検査 等)は必要です。
胆嚢がん
胆嚢がんとは
胆道がんのひとつで、胆嚢や胆嚢管に発生する悪性腫瘍のことを言います。高齢女性に発症しやすく、初期症状が現れにくいという特徴があります。そのため、患者さん自身が気づいた頃には進行がんとなっていることが大半です。なお進行期になって現れる症状は、腹痛(右上腹部の痛み)、黄疸、全身倦怠感、食欲不振、体重減少、嘔吐などです。
胆嚢癌の危険因子は、女性ホルモンを介した胆嚢粘膜障害、膵胆管合流異常(胆管と膵管が十二指腸の手前で合流する先天性異常)等です。初期のがんの場合は開腹による胆嚢摘出術となりますが、がんの進行具合により肝切除膵頭十二指腸切除等適応術式は様々です。
胆管がん
胆管がんとは
胆道に生じるがんを胆道がんと言いますが、胆道がんは肝内胆管がん、肝外胆管がん、胆嚢がん、乳頭部がんに分類され、肝外胆管に発生するがんを胆管がんと言います。胆管がんは、発生部位によって肝門部領域と遠位(十二指腸側)に分けられます。
胆管がんの特徴ですが、60代以上の高齢男性の患者さんが多く、膵・胆管合流異常、先天性胆道拡張症、原発性硬化性胆管炎の疾患があると発症リスクは高いと言われています。
主な症状ですが、早期では黄疸(皮膚が黄色くなる)ビリルビン尿(尿の色が褐色)、体重減少とされています。進行期になると、全身のかゆみ(掻痒感)、腹痛、全身倦怠感、白色便などがみられます。このがんも胆嚢がんと同様に進行がんになってから発見されることが多いです。
治療は基本的に外科的切除になり、肝門部領域胆管がんでは肝葉切除兼肝外胆管切除、遠位胆管がんでは膵頭十二指腸切除が行われます。
膵臓疾患
急性膵炎
急性膵炎とは
何らかの原因によって膵液に含まれる消化酵素により自らの膵臓が消化されてしまった状態が急性膵炎です。症状の程度は軽度~重度まで様々ですが、重症と判断された場合は、集中治療が必要となります。
急性膵炎の原因は、男性ではアルコール、女性は胆石が引き金になりやすいとされていますが、膵臓損傷、脂質異常症、副甲状腺機能亢進症、原因不明の特発性なども挙げられます。
よくみられる症状は、持続的な上腹部痛です。さらに、背部痛、嘔気や嘔吐、食欲不振、発熱なども起きます。また同疾患を発症する患者さんの2割程度の方は重症化すると言われています。この場合、膵臓以外にも炎症が広がっていれば多臓器不全、膵臓が壊死すると感染症を引き起こし、それによるショック状態、呼吸困難、意識障害などがみられることもあります。
治療は、絶飲食による膵臓の安静・大量の補液(タンパク分解酵素阻害薬、抗生剤)となります。重症膵炎の場合は集中治療が必要です。急性期を過ぎると膵仮性嚢胞(液体が貯留した袋状のもの)が生じたり、周囲の臓器が壊死し感染を生じることがあります。壊死を伴う急性膵炎の場合は、発症後期に膵周囲組織の壊死後の物質貯留により形成される被包化壊死(WON)が起こる可能性があり、壊死部分を除去する適切な治療が必要となります。
慢性膵炎
慢性膵炎とは
長期に渡って膵臓に炎症が繰り返し起こることで、膵臓が痩せて硬くなる病気(萎縮と線維化)です。膵臓の膵管(膵液の通り道)が細くなり膵臓に石ができたりることも多いです(膵石)。そのうち膵液の分泌や血糖値を下げるインスリンの分泌が低下していき、膵臓自体の機能が低下していきます。ちなみに同疾患は膵臓がんの発症リスクを上昇させます。
発症の原因の多くは、長期間に渡る飲酒・喫煙とされ、中高年男性に発症しやすいと言われています。女性の患者さんの場合は、原因が特定できない特発性慢性膵炎がよくみられます。そのほか、脂質異常症・副甲状腺亢進症がきっかけになることもあります。
主な症状ですが、初期の頃(代償期:膵臓の機能が維持されている状態)は上腹部や背中に痛みを感じるようになります。また嘔吐・吐き気もみられます。この状態が5~10年続くと、痛みは消えていきますが、膵臓の機能そのものは低下してきています(非代償期)。これによって、下痢、食物による脂肪分が混じった便(脂肪便)、体重減少のほか、糖尿病に罹患しやすくなります。
アルコールが原因の場合は治療の基本は禁酒です。その他、喫煙も慢性膵炎を増悪させる為禁煙も必要です。痛みに対して痛み止めの内服、膵液の不足に伴う消化吸収不良の症状に膵酵素の内服を行います。内分泌機能低下にはインスリン注射が行われます。他には膵管の狭窄や膵石が痛みの原因の場合は内視鏡治療を行います。
膵嚢胞性疾患
膵嚢胞性疾患とは
嚢胞性腫瘍、非腫瘍性嚢胞、嚢胞変性を伴ったその他の腫瘍を含む疾患となります。嚢胞性腫瘍には、大きく、膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN),粘液性嚢胞腫瘍(MCN)、漿液性嚢胞腫瘍(SCN)、充実性偽乳頭腫瘍(SPN)などがあります。嚢胞とは液体を含む袋状の構造物になります。
IPMNは膵管上皮から発生し粘液産生と膵管の嚢胞状拡張をきた事を特徴とし、高齢の男性の膵臓の頭の部分で発症することが多いです。多くは無症状の為、健診の腹部超音波検査や、腹部CTやMRIなどの画像検査で発見されます。発症原因は現在のところはっきりしていません。
膵臓の中には主膵管と、そこから枝分かれする分枝膵管があります。IPMNはできる部位によってできる部位によって主膵管型、分岐型、混合型に分類されます。主膵管型IPMNと診断された場合には、癌化している可能性が高いため外科手術が推奨されます。また分枝型では良性のケースが多いのですが、それでも詳細な検査等によって悪性の可能性があると考えられると、外科的切除となります。混合型については、各々の症例に基づき、悪性の疑いがあれば手術の適用となります。
膵がん
膵がんとは
膵臓に発生するがん(悪性腫瘍)のことを膵がん言います。膵がんの9割は膵液を運ぶ働きをする膵管の細胞で発生します。高齢者に発症しやすく、早期に発見することが難しいと言われているがんです。発見された時点の大半は進行がんなので、予後は不良です(5年生存率は、すべてのがんの中で最も低い)。
原因については現時点では特定されていませんが、慢性膵炎、糖尿病、喫煙、膵嚢胞、膵がんの家族歴などがリスク因子として挙げられます。よくみられる症状ですが、発症初期は自覚症状が出にくいです。進行していくことで、黄疸、腹痛、背中や腰の痛み、体重減少などがみられるほか、膵がんの前に糖尿病を発症、または悪化させる患者さんも多いです。
膵がんに対する治療は、進行度分類と切除可能分類が重要になります。