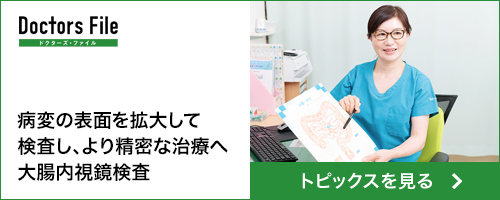内科とは

風邪をひいた、高熱が出た、お腹が痛い、吐き気・嘔吐がする、下痢、息苦しい、胸が押さえつけられるように痛いなど、急に生じた不調や、日頃のライフスタイル(過食、運動不足、飲酒、喫煙、過剰なストレス
等)がきっかけとなって発症する生活習慣病(高血圧、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症)をはじめ、体がだるい、体重が減ってきた、立ちくらみやめまいがする、動悸がする、息切れがする、息苦しい、夜眠れない、血尿が出る、排尿の回数が多い、などの症状の他、蕁麻疹や花粉症、アレルギー性鼻炎に対しても幅広く対応して診療を行っていますのでお気軽にご相談ください。
また内科は、患者さんを治療するというだけでなく、適切とされる診療科へ案内する役割も担っています。そのため、原因不明の体調不良で、何科を受診すればよいか分からないという場合もお気軽にご受診ください。
以下のような症状のある方は、一度ご受診ください(例)
- 熱、せき(咳)、痰、鼻水、喉の痛み
※熱のある方は、来院前に一度受付までご連絡ください - 食欲不振
- 胸痛、胸部圧迫感
- 頭痛
- 立ちくらみ
- 動悸、息切れ
- むくみ
- 喉の異常な渇き
- 尿の異常(出にくい、近い、血が混じるなど)
- 発疹
- 疲労感、夏バテ
- 寝付きが悪い、途中で目が覚める
- 急な体重の増減 など
内科で対応する主な疾患
風邪
風邪とは
風邪は、正式には急性上気道炎と呼ばれる呼吸器感染症です。主にウイルスに感染すること(飛沫感染 等)で、鼻水・鼻づまり、喉の炎症による痛み、咳などの症状のほか、発熱、頭痛も現れるようになります。多くの場合、症状は数日で治るようになりますが、いつまで経っても咳や熱が続く、症状が悪化したという場合は気管支炎や肺炎に進行する場合もありますので症状が長引く場合には受診してください。
インフルエンザ
インフルエンザとは
インフルエンザウイルスに感染すること(飛沫感染等)で発症します。1~2日の潜伏期間を経た後、強い寒気や高熱(38℃以上)がみられるほか、風邪のような症状(鼻水・鼻づまり、喉の痛み、頭痛
等)、全身の倦怠感、関節痛なども出るようになります。症状が悪化すれば、肺炎や脳症などを引き起こすこともあるので注意が必要です。
インフルエンザの治療薬には、内服薬、吸入薬、点滴薬があり、発症後48時間以内に治療開始することが推奨されています。
同ウイルスは感染力が非常に強いという特徴があります。したがって発症から5日程度、もしくは熱が下がって2~3日が経過するまでは、家の中で療養するようにします。
生活習慣病
生活習慣病とは
日頃の生活習慣の積み重ねによって引き起こされてしまう病気を総称して生活習慣病と言います。具体的には、偏食、嗜好品の過剰摂取(喫煙、アルコールの過剰摂取 等)、運動不足、ストレス、睡眠不足などが蓄積していくことがきっかけとなります。これらが続くことで、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を発症するようになります。
上記の疾患については、自覚症状が現れにくく、病状を進行させやすいという特徴があります。放置が続けば動脈硬化を促進させることになります。それでも何の治療をしなければ、血管狭窄による血流悪化、血管閉塞が起こるようになります。これによって、脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、閉塞性動脈硬化症など重篤な合併症(ある病気の発症がきっかけとなって起きる別の病気)を発症するようになります。
健診結果で数値に異常があれば、速やかな受診を
このような状態にならないためには、定期的に健康診断を受診することが大切です。その結果、生活習慣病に関係する数値(血圧、血糖値、コレステロール値 等)に異常があると医師から指摘を受けた場合は、体に何の異常がないと感じていても一度医療機関を受診されるようにしてください。
当院でも生活習慣病を発症している患者さん、あるいは生活習慣病の予備群であるという方を対象に治療や予防対策を行っています。内容としては、食事療法や運動療法などによる生活習慣の改善、治療が必要な場合は薬物療法を行っていきます。
主な生活習慣病
高血圧
高血圧とは
血圧が高い状態が続くと血管に常に負担をかけ、動脈硬化を進行させてしまいます。動脈硬化が進むと、心筋梗塞、狭心症、脳出血、脳梗塞、動脈瘤、眼底出血などの原因となります。また、心臓は心臓肥大が起こり、心不全になることもあります。これらの疾患のリスクを下げるために、血圧のコントロールは不可欠です。高血圧は、遺伝的な要素や過剰な塩分摂取、肥満、習慣的な喫煙や飲酒、運動不足、ストレスなどさまざまな要因が重なって発症すると考えられています。当院では生活習慣の改善(食事指導・運動療法)の指導の他、降圧剤による内服治療を各々の患者さんに合わせて治療を行います。
脂質異常症
脂質異常症
脂質異常症とは、血中の中性脂肪や悪玉(LDL)コレステロールが多過ぎる、または善玉(HDL)コレステロールが少なすぎる、状態を呈する病気のことを言います。悪玉(LDL)コレステロールは、血管内の過剰なコレステロールを血管の壁に沈着させ動脈硬化を起こしますが、善玉(HDL)コレステロールは血管内に貯まったコレステロールを肝臓へ戻すように働きます。
脂質異常症自体は自覚症状はありませんが、そのまま放置しておくと、脂質が血管壁にたまって動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞が起こる可能性が高くなります。自覚症状がなく進行するため、早期発見が大切です。
発症の原因は、過食、肥満、運動不足、習慣的な喫煙や飲酒、遺伝的要因など挙げられます。
脂質異常症の治療には生活習慣の改善(食事療法、運動療法)、の他中性脂肪やコレステロール値を下げる内服治療を行います。脂質異常症も当院にご相談ください。
糖尿病
糖尿病とは
慢性的に血液中の糖分が基準の数値を上回っている状態を糖尿病(1型糖尿病2型糖尿病に分類)と言います。血液中の糖分は、膵臓から分泌されるホルモンの一種であるインスリンの分泌量が減少したり、インスリンのはたらきが弱くなったりするため、血糖値が高い状態が続くようになります。主な症状ですが、発症初期は多くは自覚症状はありませんが、病状が進行すると、全身の倦怠感、体重減少、頻尿・多尿、異常な喉の渇き、などがみられるようになります。それでも放置が続けば、細小血管障害による合併症(糖尿病三大合併症:糖尿病網膜症・糖尿病神経障害・糖尿病腎症)、動脈硬化促進による血管障害(心筋梗塞、脳梗塞 等)、などの重篤な病気を発症することもあります。
治療の目的は、血糖値を基準の数値まで下げ、それをコントロールすることにあります。早期に生活習慣の改善(食事療法や運動療法)を行い、内服薬による治療やインスリン注射(1型糖尿病、2型糖尿病の一部)などによる血糖のコントロールが必要です。
痛風(高尿酸血症)
痛風とは
痛風は主に血液中に含まれる尿酸が過剰に増えることで、細胞内のプリン体が生成され、針状の結晶が形成され、この結晶が関節に蓄積されることで、一部の関節に腫れや激痛の症状がみられる疾患です。なお血液中に含まれる尿酸値が7.0mg/dL以上と判定されると高尿酸血症と診断されます。
プリン体は主にビール、レバー、海老、アジの干物、干し椎茸に多く含まれており、過度の摂取には十分な注意が必要です。治療ですが、痛風発作による痛みや腫れを治めた場合は、対症療法による薬物療法としてNSAIDs(非ステロイド抗炎症薬)を使用します。その後痛みや腫れが治まったら、根本の原因でもある尿酸値を下げることを目的とした治療を行います。